「井上ひさし先生との仕事、その1」で、構想から執筆開始までの状況を書きました。
続きを書かなくてはと思いつつ、師の遅筆を真似したわけではありませんが、原稿が無いのに稽古が始まった地獄の日々を思い出し、辛く、苦しく、しばらく書くことを躊躇しておりました。
が、ようやくここに意を決し、台本が無いのにはじまった稽古の日々を書いていこうと思います。
それと、ブログを始めてから10本位書いて、少しネタ切れ感もあって、困った時の井上ひさし先生と言うのも、正直なところでございます。
台本が無いのに、稽古が始まる‥
「台本が無いから、明後日から始まる稽古は3日くらい延期しようか?」
「いやいや、そんな事をしたら俳優の不安を余計に煽ることになるから、稽古始めた方が‥」
「始めるったって、どうやって?」
台本が無い時の稽古開始2日前は、演出家、舞台監督、プロデューサーの3者で、いつもこんな話をしていました。
話はどうやって始めるか?
で、最終的には次のような段取りでした。
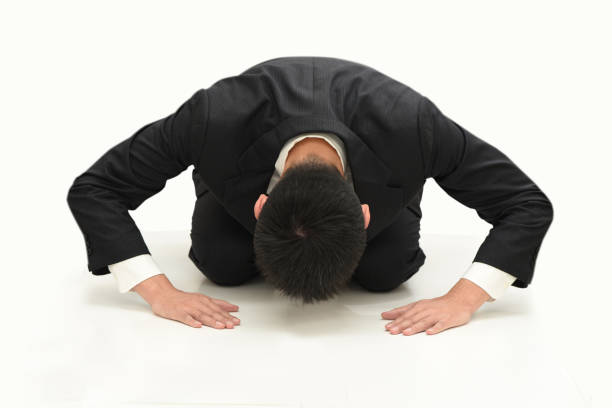
ってか、最初の3枚です。
1、プロデューサーが冒頭の挨拶というかお詫び
この写真ほどではありませんが、劇団ではプロデューサー全員がスタッフ、キャスト、マネージャーの前で、謝るところから稽古が始まります。
そして、井上ひさし先生との仕事、その1で書かせもらった「プロット」の中身、現段階での構想を話し、予想台本完成日(Xでー)を話しましす。
「台本完成は初日の8日前です」というように宣言しますが、当たったことはありませんでした。
これに比べれば、天気予報や競馬の予想の方が遥かに簡単な気がします。
だからというわけではありませんが、稽古初日の稽古場には結構美味しいサンドウィッチが50個、コーヒーメーカー2台で、常にコーヒーが飲める状態にしてあり、プロデューサーのせめてものお詫び‥
それで「明日の朝には、皆様のご自宅に、今夜、出た原稿をお届けしておきます!」
と約束をしてました。
これは、本当にやりました。
当時、一般家庭にFAXがまだそんなに普及していなかったので、制作部員が手分けして俳優の家のポストに入れていくのでした。
2、顔合わせ開始と挨拶
稽古開始の日は、顔合わせも行いますので、3人掛けの折りたたみ机を、カタカナのロの字型に繋げて、俳優と演出家、メインプランナーに座ってもらいます。
それを外側から囲むように、俳優の後ろにマネージャー、メインプランナーの後ろに演出スタッフ、
少し離れて、独立した感じに制作デスクが置かれています。
はじめにプロデューサーが挨拶‥お詫びをした後、全員のお名前、役名、スタッフは担当を紹介いたします。
続いて、演出家が‥普通は演出方針など言うのですが、台本がないので、
「兎に角、私に付いて来てください、大丈夫です!」
と元気にハッタリをかまし、俳優を安心させます。
もっとも、俳優にしてみれば、台本が無いということは、何も持たずに全裸で戦場に送られるに等しく、台本が0枚のときは俳優全員、顔面蒼白でした。
1枚でもあるとこれが全然違うのです。
3、台本の冒頭がある場合は、その部分の本読み、ない場合は割愛。
稽古開始日は井上先生も承知していて、その日の開始時間、午後1時に少しでも稽古場に原稿を入れようと頑張ってくれるので、大抵、稽古開始日の午前10時ごろに、執筆先から劇団事務所に原稿が3枚、FAXが流れて来ました。
「万歳!万歳!」制作部員たちは鬨の声をあげました。
これから始まる稽古の事を考えるると 気が重かったのですが、いっときでも、それを忘れたかのように、鬱屈した心を解放し、騒いで稽古場へ行く力にしていたのです。
原稿がたとえ1枚でも出てくれば、その次がある!と確信が持てます。
0枚だと、本当にこれ台本できるのか? メチャクチャ心細いのです。
とはいえ、3枚ですと稽古場では演出助手がト書きを読んで、最初のセリフを発する俳優が一言だけしゃべって‥終わりです。
この時点では、そうは言っても初日にはまだ1ヶ月あるので、さて、続きは?
という感じで、まだ、少しだけ余裕があります。
これが0枚の時は「お通夜」です。
4、演出スタッフによる、むりくり俳優の採寸作業。
これは舞台監督から、なんとか時間を潰さないと、稽古開始日が10分で終わってしまう。
というので、なんとか、何かないか? あっそうだ‥・

ということで、急遽、入れてもらった作業です。
まあ、遅かれ早かれやることですので、ここでやって、少し俳優の不安を緩和しようという作戦でもありました。
実は、この時、採寸をしている俳優以外は、順番待ちですので、稽古場でコーヒーを飲んだり、サンドウィッチを食べたりして比較的コミュニケーションが取りやすい時間なのです。
ただし、プロデューサーはあまりニコニコしていてはだめでして、誰かが話しかけてくれるまで、じっと目を伏せていなければ「あっ、本ないくせにニコニコしてる!」とか、心無い人に言われてしまいますので‥。
案外、地味で辛い商売です。
4、演出助手から、明日からの稽古予定を発表して終わり
でもこれ、どんなに時間をかけても1番から3番までは、10分もかからずに終わってしまいます。
4番の採寸で時間を取ってもらっても‥まあ、15分から20分ですので、稽古開始は30分で終わりです。
時々、台本が若干あって、ト書きから冒頭のセリフの二行なんていう時は、本当はそんなこと感じている場合ではないのですが、光明が見えている感じでした。
最後に稽古場で稽古進行を司る、演出助手が明日からの稽古スケジュールを発表します。
演出助手「それではお聞きください、本来ですと4日から5日ほど本読みを行いますが、台本執筆が現在のような状況ですので、ある程度5枚とか6枚とか出来た状況で、立稽古に入ります」
「しばらく、この本読みと立ち稽古の同時進行を続けていきます、なお、明日、明後日は稽古を休みにしますので、次回、明々後日の13時から稽古開始します、では本日はお疲れ様でした」
その声を合図に、キャストはマネージャーと共に三々五々帰っていきます。

もうひとつあった裏のドラマです
みんな帰った後の、誰もいないがらんとした稽古場にいると、
本心から、ここから外に、現実の世界に行きたくないと思いました。
執筆=井上ひさし先生の場合
井上ひさし先生(以降、作家という表現も併用します)作家の原稿執筆スタイルは、午後1時ごろ起床し、シャワーと食事の後、午後3時ごろから、翌朝5時頃まで、途中食事時間を省くと、大体12時間ほど執筆していました。
劇団で待つ我々の元に、作家の書斎からFAXが送信されて来るのが、午後7時、午後11時、午前3時、午前5時の4回でした。
もちろん、時間通りにピタッと来るわけではありませんが、作家が1回送信して来るごとに、電話があり送り込まれた執筆部分の説明や、演出家や音楽家への伝言があります。
その時に、稽古場の様子を聞いて、執筆内容に活かすことがありました。
最後に「では次回は午後7時に」と言って電話が切られます。
ただし、数分、時には1時間ほど遅くなってFAXが来ることもありました。
長年の経験から約束の時間を過ぎてもFAXが鳴らない場合は、執筆がとても順調で、途中でやめてF AXを送る時間が惜しいと、どんどん書き進んでいる時でした。
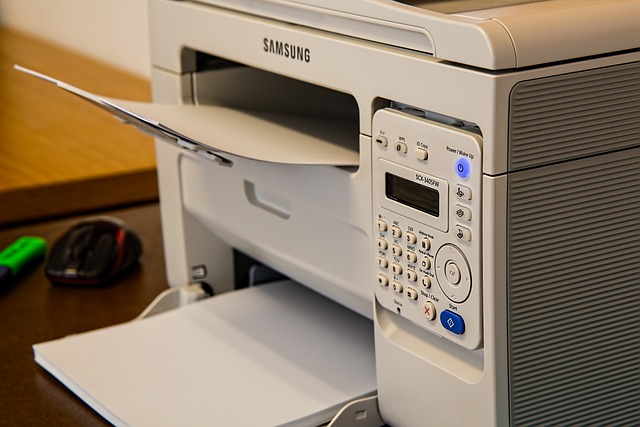
逆に早い時は、何か作家が内容に行き詰まったり、最悪の時は体調を崩したりした時は、約束の時間より早く電話が入ったりしました。
ただ、平均して400字詰め原稿用紙に換算して1日5枚から7枚のペースで、原稿が上がってきました。
作家は執筆にワープロを使用しており、以前、手書きの時は400字詰め原稿用紙でしたが、その時は500字や550字のワープロで執筆された原稿が送られて来ました。
脱稿想定枚数は400詰原稿用紙換算で、120枚がプロデューサー、同じく120枚が演出家、舞台監督は140枚を想定していました。
大体、プロデューサーと演出家は希望的な数字で、舞台監督は冷静な数字になります。
大道具作っちゃおうかな、やめようかな、どうしようかな、もお間に合わない! えい!1000万円
作家のプロットで、最初から最後まで同じ場所での作品なら、最後のシーンまで舞台装置は変わらないと思うので、作り始めてしまいます。
そうしないと、本番の3週間前から作り出さないと、大道具が本番に間に合わなくなるのです。
問題なのは、場面が変わっていく時です、下宿部屋、カフェ、アパートの一室、病院の庭、自宅、など場面がどんどん変化する作品は、もうお手上げですが、その際に頼りになるのが作家の台本設計図ともいうべき「プロット」です。
そのプロットを元に、大体の舞台装置をプランして、最後はプロデューサーが作家にその舞台装置を見せに行きます。
作家から「こんなんじゃありません!」とか言われたらやり直しだな、そうしたらもう一回、スタッフ会議で練り直さなければ‥と、重くなっている気を引きずりながら、作家に舞台装置のイメージ図を見せると、作家はこちらの心配をよそに、キャッキャッ言いながら嬉しがっています。
「凄い!凄い!いいですねぇ、カッコいいです!」
「先生、どこか問題があったら言ってください」
「ないです、ないです、これ、机の前に貼っておいて、これに合わせて書きますから、中島さん、安心してください! いやあ、出来た、出来た、中島さん、これでこの芝居はもう成功が約束されたと同じです!」
これはテンションが高い時の井上ひさし先生で、勿論、多少のジョークは入っていますが、作家は「この舞台装置で舞台のイメージがより鮮明に近づいてきました」
とか
「作品を書く上で、大きな道標です!」
と喜んでくれました。
これでプロデューサーとしては、それまでクヨクヨ悩んでいた、大道具を発注する決断がつきます。
ええいっ!大道具発注だあ! 1000万円也。
稽古再開‥した後は‥
稽古場は2日休みの後、始まりました、その時は原稿用紙にして20枚出来ていましたので、少しだけですが、稽古を進めることが出来ました。
と言っても、20枚の内、冒頭の2枚はト書きですから、実質18枚です。
舞台の場合、昔は400字詰め原稿用紙1枚が、舞台上では約1分という見通しだったのですが、最近、観客の問題なのか時代なのか、速度が早くなってきています。
ですから原稿用紙3枚で2分で考える時代です。
18枚ですと、12分です。
演出助手が「それでは稽古を始めます、第一幕、第一場、頭(冒頭)からまいります」
って、そこしかないんだから、わざわざ、第一幕って言わなくたってと思うってツッコミたくなるのですが、、こんな状況では、プロデューサーは小さくなっていなければいけないので、静かにしています。
地味で辛い商売です。
「はい、では本日の稽古はこれで終わります」演出助手からのコールです。
時計は13時40分です。

本来ですと、13時から21時までが稽古時間ですので、7時間以上早く終わってしまいました。
夕方ですと、みんな連れ立って近くの居酒屋とか行くんだけど、なんとなく皆さん手持ち無沙汰で、
なんだか、親に捨てられた子猫のように心細そうに固まっていました。
時々、恨めしそうにプロデューサーをチラ見してきます。
地味で辛い‥。
台本を待つ俳優の状態
稽古が再開された後の数日間は、比較的のんびりとした稽古が続きます。
というか、台本が無いのでそう見えているだけで、俳優はそうしている間にも、初日が迫って来るので教科書が無いので受験しなければならない、受験生のようでした。
どうしていいのか分からない状態の俳優は、幾つかのタイプに分かれました。
1、ただ、オロオロして段々鬱になっていく俳優
これは、稽古場に来るのが最初は稽古開始の1時間前だったのが、30分前になり、15分前になり、やがて1分前くらいになってきます。
特徴的なのが、稽古場に入ってきても挨拶だけで、あとは誰とも話をしないで、虚な目で窓の外をぼんやり眺め、時々、苦しそうな顔になります。
実はこのパターンが一番危険で、突然、台本が覚えられなくなったり、セリフが出てこなくなったりして、そのうち体調を崩してしまうタイプです。
プロデューサーはこういう俳優を状態を真っ先に把握し、色々なフォローをしていきます。
具体的には「大丈夫ですよ、皆さんがちゃんとセリフが体に入って、芝居がしっかりできといると判断するまで、幕は開けません」と言って、とにかく、緊張をほぐしていきます。
プロデューサーの本音としては「この時点では初日をズラすなんてことは考えていません。
ギリギリの時は、「大丈夫、あなたの演技なら幕を開けることができます。心配しないで、ちゃんと出来上がってます!」
あとは、井上ひさし作品の新作を何度か経験している俳優にお願いして「大丈夫だよ、なんとかなるよ」と励ましてもらったりしていました。
それでもダメだと判断したら、最後は初日の延期という事になります。
何度もやりました。
2、どーんとしている俳優
比較的自分の演技に自信を持っている俳優は、どーんと構えていて、プロデューサーから見ると、頼もしい限りです。
私が一緒に仕事をした俳優で、「段田安則」さんがこういうタイプでした。
稽古場にも1時間くらい前に入って、稽古着(ジャージの上下)に着替えると、おもむろに台本と言っても、原稿のコピーですけど、それを机の上に広げながら、買ってきたパンをゆっくりと食べ始めます。

「段田さん、原稿がなかなか入らなくてすみません」と言うと
「へぇ、私はただ覚えてしゃべるだけですから、なんとも無いですよ」
モグモグしながら、表情は笑っています。
みんなこの状況の中で、精神的に覚えてしゃべるのが出来なくなっている訳で、
肝がすわっている俳優さんでした。
めっちゃ冷静なタイプ
稽古が終わった後に、作家から上がってきた原稿は、翌日の稽古開始までに俳優が読めるように、最終の1つ前、午前3時にまでに上がって原稿を大急ぎでコピーして、毎日、俳優の自宅のポストに投函していました。
ですから、私は大勢の俳優の自宅を知ってます。
大豪邸もあれば、そうでないものあり、やはりテレビ、映画で活躍している人のお家は、豪邸でして、
結構いい感じの脇役の人も、ちょっと豪邸でした。
舞台1本でやってます。
と言う俳優さんのお家は普通か、ちょっとビ・ン・ボ・ウっぽい感じでした。
これじゃあ、テレビとか映画に出たいっと思うよな‥
中には、眠れないと言うのもあったのかもしれませんが、私たちが原稿をポストに投函するのを知って、待っている俳優さんもいました。
私の経験では、レジェンド俳優の「小野武彦」さんがそれです。
明け方5時少し前、小野さんの自宅のポストにそっと入れるのですが、どうしても少し音がします。
そっと、そっと去ろうとすると「中島さん!」
見つかった‥。
まだこれから、演出家の家と「江波杏子」さんの家に届けなくちゃならないのに‥
「ちょっと、いい? 上がってってよ!」

「いえ、もう、遅い‥というか、早いですし‥?」
「ちょっと、ちょっとだから」
仕方なく上がらせてもらうと「ビールって訳に行かないから、朝だから牛乳でいい?」
とコップに入った牛乳を出されました。
「でさ、この後の場、どんな感じ? 井上先生なんて言ってるの? 次の場は俺の場かと思ってんだけど」
「そうですね、小野さんの生い立ちが語られる場ですね、庶民代表という感じで」
それを聞くと小野さんは、やっぱりそうか、と合点がいった顔をしながら何度か頷いて
「ってことは、その次が塩作りの話で、その次、つまり最終景のひとつ前が、江波さんの場だな、うーむ、江波さん大変だな、まだ、そこに来るまで、1週間くらいかかるよな、ってことは初日5日前だから‥大変だな」
そう言いながら、名探偵のような仕草で顎を撫でながら、何度も何度も頷きました。
「江波さん、フォローしてあげて、俺も傍から支えるからさ」
自分のことより、全体のことや他人の事が気になるようで、俳優やめても凄いプロデューサーになれそうです。
眠れないを繰り返す俳優さん
稽古場にも普通に来て、みんなとも話をして、血色も良く、どこから見ても健康そうに見えるのですが‥よく見ると、少し寝不足気味かな? どうかな?という感じの俳優さんです。
名誉の為に、実名は伏せますが、親子2代でしかも兄弟も俳優という、俳優一家に育ったサラブレッド的な40代の俳優さんでした。
朝方受け取った原稿を必死で覚えるために、稽古場の隅でひとりで「モニョモニョ」やっているのですが、気がつくと「スーッ、スーッ」寝息が聞こえてきました。

共演の女優さんが「わかるわぁ、あんなに寝てたら、夜寝られないわけよね」
それで稽古場が大爆笑になったのですが、その俳優さんは全く起きる気配がありませんでした。
でも、夜、心配で眠れないというのは本当のことだと思います。
それで、昼間、同じ俳優仲間といると安心して、眠ってしまったのだと思います。
台本がギリギリの時、俳優さんそれぞれのセリフの覚え方
通常、台本は製本されたものが、稽古が始まる1ヶ月前には俳優やスタッフの元に届けられます。
しかし、新作公演の場合、稽古開始に台本が間に合わず、毎朝、5枚、6枚の原稿がポストに届き、それを午後1時からの稽古開始まで、必死に覚える作業が続きます。
俳優さんによって、その覚え方や覚えるスピードが違います。
ひたすら書いて覚える俳優
あまりいませんが、ただただ書いて、書いて、書いて覚える俳優さんがいます。
大抵、いい大学を卒業している受験秀才です。
覚えるのに時間は掛かるようですが、一旦覚えたら、なかなか忘れないようです。
問題点は自分のセリフを優先的に覚えるので、誰のセリフの次が自分の番なのかを覚えるまで、少し時間がかかります。
一度読んだだけで、覚えてしまう女優
はっきり申し上げます。
元宝塚の男役スター「安奈淳」さんです。
彼女とは井上ひさし作・木村光一演出「シャンハイ・ムーン」という新作で、ご一緒しました。
稽古開始直前にこまつ座の事務所から4枚原稿が入り、13時からの稽古の時に俳優の皆さんに配りました。
その時、私は演出助手をしていましたので、演出家と相談し、 俳優に新しく来た原稿を読む時間として15分間取りました。
その間、安奈淳さんは私の後ろの机でサンドウィッチを頬張りながら、原稿を眺めていました。

10分後、本来なら本読み稽古をするのですが、演出の木村光一さんが
「初日まで時間がないから、もう立ちましょう」
そうコールがあり、俳優たちが稽古場に立ちました。
皆さん、10分前に手にした原稿を持って、セリフを言い出しました。
その時、ひとり原稿を持たず、しかも、セリフを一字一句間違いなくしゃべったのが安奈さんでした。
皆絶句「安奈さん、なんでこんな短い時間に‥」
「私、宝塚時代、上の劇場で本番やってる最中に、自分の出番じゃない時は、下の稽古場行って、来月の演目の稽古してたから、とりあえず覚えるって訓練できてるの」
そういえば、宝塚出身の女優さんたちは、舞台袖での早替わりなんかも早かったでした。
宝塚歌劇団の訓練、恐るべしでした。
まるで「虎の穴」です
セリフをひたすら声に出して覚える‥ちょっとだけ、周りに迷惑な覚え方
これは、四六時中「セリフを喋るつづけて覚える方法です」
お亡くなりになってしまいましたが、私が一緒に仕事をした俳優では「藤木孝」さんが、終始セリフを暗誦していました。
それこそ四六時中、場所も時間も関係なく‥。
稽古場まで、都営地下鉄でいらしていましたが、混んでいる電車内で、ある場所だけ人が居ない空間がありました。
そこから、何やら大きな声が聞こえてきます。
「私、熱烈な愛読者であります。歯科医です!」
「母は結核で‥肌が白くそして頬がほんのり赤みがさして‥いきなり、拉致されて‥」
藤木孝さんでした。
車内にいた乗客たちは、なるべく見ないようにしながらも、気になって藤木さんと目が合わないように、チラチラ横目で見ていました。

そして電車が駅に着くと、セリフを喋りながら改札を通り、喋りながら道を歩いて稽古場にやってきました。
稽古中のその状態は、藤木さんのライフワークになり、常にセリフを喋っていないと落ち着かなくなってしまいました。
稽古から帰る駅のホームでもひとりでセリフをしゃべっていました。
それは芝居の幕が開いた後も続き、旅公演先でもそんな状態でした。
問題は旅公演の移動の時でした。
新幹線の中で突如「魯迅先生には、歯をしっかり治していただきたい!」
「そして、母は亡くなりました!」
などと大声で言い出すので、周りの人が驚いて、車両から逃げていく人もいました。
最新機器での暗記
セリフの暗記に、受験生が暗記するのに使われた「キオークマン」という機械がある。
色々なタイプがあるようだが、ヘッドフォンとマイクロフォンがあって、それで終始ブツブツ喋って暗記をしていた俳優がいた。
名優、怪優と言われた「すまけい」さんです。
稽古場への行き帰り、真剣になって暗記をしていました。
すまけいさん曰く「かなり効果がある」という事でした。
 | 価格:10175円~ |
俳優がセリフを覚える3要素
稽古場のスタッフ席にいて、「本読み」から「立ち」になり、やがて通しと稽古が進むのを見ていると、俳優がセリフを覚えるのに必要な3要素があることに気がついた。
セリフというのは、当たり前だが「話し言葉」になっている。
それを舞台の上で喋るのだが、その時に必要な3要素が、実は覚えるため役に立つ3要素でもあります。
頭の記憶
これは単純に暗記するための頭脳です。
覚えるのが早い人、遅い人いらっしゃいましたし、まあ、年齢なども関係があるでしょうが、1か月も稽古をしていれば大抵覚えていました。
ただし、後3日で本番!
と言われて「これセリフ」というと、途端にプレッシャーで覚えられなくなる俳優さんもいました。
この時は「正確に覚えなくては!」と考える俳優さんより「なんか、それらしき事をいえばいいや!」と考える俳優さんの方が早かったです。
身体の記憶
これは、よく俳優さんがいう事でしたが、セリフを忘れていると思っても、舞台上のそのセリフを言う場所に行くと、自然に体の中からセリフが出てくる。
どうも、頭だけで誦じてはダメで、覚える時もその時の場所や立ってるのか、座ってるのかと言う身体の状態と一緒に覚えると早く覚えられたようです。
暗記する時も、その時の身体の状態、状況を思い出しながら覚えていく方が、早いと言う事です。
感情の記憶
身体の記憶と似ていますが、その時の自分の感情、よく言われる喜怒哀楽と一緒に覚えると、随分早くそして豊かにセリフが覚えられ、しかも、セリフを言うことがとても面白くなるようです。
ベテランの俳優さんは、怒りの中にも悲しい怒り、寂しい怒り、怯えから来る怒りなど、嬉しい怒り様々な表現を操っていました。
そう言う時の俳優さんの演技は、何かが降りて来たようで、確かにとても豊かで、素晴らしかったです。
いわゆる、名演技というか、神がかっていました。
つづく
井上先生の執筆状況と稽古場の状況を、書いて、稽古場内の様々なエピソードや、スタッフとの打ち合わせ、上演劇場である紀伊國屋ホールの支配人との話など、さらに公演延期を決めていった状況などまで、書いていこうと思っていたのですが、ここまで随分と文字数を使ってしまいました。
井上ひさし先生との仕事、その2はここまでにして、ここから初日に向かっての怒涛の稽古の状況は、近々、その3で描かせていただきます。
それまで皆様、しばしのご猶予を。
いつか書く予告
井上ひさし先生との仕事、その3
「初日開くの? ダメかも」「じゃあ初日はいつ?」「初日延期の新聞記事が段々小さくなって」
などの巻
新国立劇場元プロデューサー
中島豊
付録

普段、裏方で表に出ることのないプロデューサーですが、
本番中にトラブルが起きたりすると、観客の前に出て説明することがあります。
この時は、機材のトラブルで少し開演が遅れている説明をしているところですが、客席から「どのくらいかかるの?」とか
「機材って何?」とか聞かれることがあります。
そんな時は「それはですね‥‥あのぉ‥ええいっ!もう本音言いますとね‥」
などと私は答えていました。
本当は幕の裏での対処の時間を稼ぐために、いろいろお話をし始めたりしまして、長い時は5分、10分色々おしゃべりしてまして、そのうちに解決したりしました。
お蔭様で「あの人、面白い」とか裏でも「トラブルが起きたら中島だ」とか言われてました。
そんな時は終演後に出口に立っているとお客様から「ご苦労様でした」とか「面白かったですよ」とか‥それは芝居に対してなのか、私の説明に対してなのか分かりませんが、多分、後者だと解釈して
「ありがとうございます!」とニコニコ応えていました。








