映画やテレビの場合ですと、本番でセリフを忘れた場合でも、監督やディレクターが、
「はい、カット!」
と言って、最初からやり直します。
舞台の場合はお客様がいますので「すみません、もう1回最初からやり直します」
という訳にはいきません。
どんなことがあっても、なんとかやり切らねばなりません。
実際のプロの現場では、どのようにやり切るのでしょうか?
あまり、大ぴらにはできませんが、少しお話しいたします。
台詞を忘れる瞬間
セリフを忘れる場合、業界では「セリフに詰まる」とか「セリフが飛ぶ」とか言います。
舞台の場合、1ヶ月間、1日8時間くらい稽古をして本番に臨みます。
1ヶ月も毎日毎日、おんなじ事を言っていたら、どうやったって覚えるはずです。
はずなのに、どうした訳か本番中の俳優からセリフが出てこないことがあります。
その瞬間、舞台に出ている俳優だけではなく、裏にいるスタッフまで固まります。
今まで舞台から聞こえてきていた会話が、突然聞こえなくなり、シーンと無音になるからです。
何が起きた?
この瞬間、舞台上の俳優はさぞパニックかと思うと‥大きく二つにパターンが分かれます。
まず、セリフを忘れた俳優が「自分がセリフを忘れている自覚がない時」と「自分がセリフを忘れた自覚がある時です」
こういう時、セリフを忘れた自覚のない俳優が「一番堂々」としていて「次誰だよ」って感じで待っています。
逆にそれを見た周りの俳優がパニックになります。
「やばい、こいつ、自分がセリフ忘れている事、分かってない」
周りの俳優がなんとか場を繋ごうと、必死になればなるほど、変なことを喋り出したり、ぐるぐる動いたりとパニックになります。
終演後、劇場を後にする観客たちが、
「あの俳優、なんか変なこと言ってたわよね、セリフ忘れたんじゃない」とか
「あの人、焦ってウロウロしながら必死で思い出そうとしてたわよね、セリフ」
とかなんとか、場面を繋ごうと頑張った俳優が「セリフ忘れた俳優」の汚名を被る事になります。
忘れた当の本人は、ケロッとして「今日、本番でセリフ忘れたのだれ?」と平気で聞いてきます。
💢‥あなたです‥
セリフを忘れた時の対処法、あれこれ
俳優は舞台上で時々セリフを忘れます。
何回もやっている舞台で、一度も忘れたことがないセリフが、出てこない。
原因も様々な要因が重なって起きるので、どれか1つというわけではありません。
「あれ、ここ昨日はめっちゃ受けたのに、今日はだめだな」
「やばい、なんか今日、舞台の上が寒いな」
あるいは「今晩、この女優をなんとか口説いて、あわよくば‥」

「あれ? セリフ俺? あっ、やばい、なんだっけ」
なんてことを一瞬でも考えた途端、セリフが出てこない!
それこそ奈落の底に叩き落とされたようになります。
まあ自業自得と言えばそれまでですが、しかし、目の前にはお客様がいらっしゃる。
それを考えると、このまま忘れて黙っている訳にはいかない。
さて、そうなった時、プロの俳優はどのように対処しているのでしょうか?
ハッキリ申し上げて、いくらプロの俳優でも、1ヶ月の稽古期間中に「もし、セリフを忘れたら、ここはこうやって誤魔化そう」などとという稽古はしていません。
ですから、セリフを忘れたら、こういう時はこうやって、お客にバレないように頑張りましょう。
なんて方法はありません。
実際の舞台で起きたケースをお話しいたします。
その1 会話の中でのセリフを忘れたケース
これは、相手役が1人、或いは複数人いての会話の時に、セリフに詰まった時のケースです。
実はセリフ忘れの場合、一番、被害が少なく助かりやすいのがこれです。
と言うのは、相手役がいるので、どこからか助け舟が出ます。
「‥‥‥」とセリフに詰まった場合、とにかく相手の目を見つめます。

焦っているので、大抵は意味不明に睨んだりします。
すると相手役が察知して
いかにもセリフのように「分かった!お前はこう言いたいんだよな?」と言って、相手役のセリフを言ってくれたりします。
言われた本人は、その瞬間思い出して「そう、そうなんだよ!」とか言いながら、内心ほっとして何事もなかったかのように、演技を繋げていきます。
勿論、終演後、一杯奢ることになります。
これが、セリフを忘れた場合の一番軽い状況でした。
その2 忘れた本人が自覚していないケース
少々厄介なのが、セリフを忘れた本人が忘れたことに気が付かない時です。
順調に進んでいたセリフの流れが、突如止まって、空白の時間が流れます。
舞台上、恐怖MAXです。

忘れた張本人は、この間(ま)は一体なんだろう?
と思いながら、次のセリフは誰だったかな?
と考えています。
対して、周りの俳優は、私の経験では3種類に分かれました。
甲)まず「えっ? 誰だ? もしかして私が忘れている? えっ、なんだっけ、セリフ」
と、セリフを忘れたのは、自分では無いのに自分かと思い、ひとりパニックになる俳優‥。
この俳優は、客席から見ると、不自然な動きや表情なので「セリフを忘れた俳優はあの人だ」
と思われてしまいました。
乙)もうひとつは、誰がどんなセリフを忘れたか、しっかり分かっていて、なんとかしようと考える俳優です。
大抵この俳優は、相手役のセリフの冒頭部分を小さな声で囁きます。
例えばセリフが「名前からすると、オランダ人でしょうか?」(井上ひさし作・『夢の裂け目』より)
だとすると「うーむ、な、ま、え、うーむ」と小さな声で助け舟を出します。
しかし、相手役は自分がセリフを忘れた自覚が無いので、こいつ何言ってんだ?という顔をします。
観客からは、この助けようとした俳優の方が、セリフを忘れて、何か聞き取れない声で、違う事を一生懸命言っているように見えました。
結局この時は、舞台裏に隠れているプロンプターが役名とセリフの冒頭を何度か声に出して、セリフを忘れている俳優に気がつかせました。
舞台に近い客席には聞こえていました。
笑いが起きたのです。
でもまあ、ここまでのトラブルは、時々ある、まあ普通のトラブルです。
何より怖いのがセリフの言い間違えです。
忘れるより怖い、セリフの言い間違え
これは、本来のセリフとは違うことを言ってしまうのですが、シーンによっては立ち直れない状況になりました。
私が目撃したのは、今やレジェンドと呼ばれる名優「笹野高史」さんが、まだ30代の頃、六本木にあった「自由劇場公演」で、ギャングの親分の役をやっていました。
舞台上には笹野さん演じる親分と、親分が子供の頃から面倒を見てやっていた、実の子供のような子分との二人だけです。
シーンは、今から敵対するギャング団が大挙して、笹野さん演じる親分の命を狙いにやって来たというところです。
敵のギャング団100人が、すでに笹野さんの事務所を取り囲んでいます。
守る味方は15人‥
これから始まる撃ち合いで、笹野さんたちには壮絶な死が待っています。
可愛い子分たちとの永遠の別れを覚悟する親分の笹野さん。
そんな親分が流す涙を見ながら子分が、
「命に変えても親分をお守りいたします!」いい場面です
ところが、どうしたわけか子分が、
「命を守っても、親分です!」
一瞬、客席も「?」となりました。
子分役の俳優も、一瞬「しまった」と言う顔をましたが、何事もなかったように、なんとかやり過ごそうとじっとしていました。
親分役の笹野さんと、子分役の俳優さんとがじっと目を合わせています。
長い間がありました‥そして
「命を守ってもだとぉ?」笹野さんが、思わず言ってしまいました。
その瞬間、客席は大爆笑です!
子分役の俳優は真っ赤になりながら「いえ、命をしゅてても、、、親分!」
そう涙声で言うと、舞台袖に引っ込んでしまいました。
舞台には笹野さんひとりです。
客席の笑いは収まりません。
笹野さんはなんとか立て直そうと、後ろ向いて、深呼吸し持ち直しと、前を向きました。
さあ続けようとすると、客席はまだ笑っています。
笹野さんも思い出して、たまらず吹き出し、再び後ろを向いて、肩を震わせ‥。
そんなことを数回を繰り返されました。
その様子を見た観客は、ますます笑いが収まりません。
何度か立ち直りにトライした笹野さんでしたが、ついに、客席に向かって深々と頭をさげました。

その瞬間、客席から笑いと共に大きな、大きな拍手が湧きました。
笹野さんへの応援と、ライブならではのハプニングの面白さ、
私も客席にいたのですが、お客さんの笑いと拍手の中に、笹野さんを応援する気持ちと、なんだか得した気分と、それを観客みんなで共有できた、楽しさが伝わってきました。
でもこれは、笹野高史という名優だから、出来たのだと思います。
普通はそのままぐしゃぐしゃになって、失笑のうちに無理やり「暗転」になって、その俳優はしばらく立ち直れません。
門外不出のセリフ忘れ防止大作戦
俳優といえども、生身の人間です。
セリフを忘れたり、違う事を言ってしまう事はあります。
特に、台本の完成が遅く、稽古時間があまり取れないうちに、幕が開いてしまった時や、1人で何ページもある膨大な長セリフを喋る時、そして、誰も助けられないのが1人芝居でのセリフ忘れです。
どうしてもと言う場合、色々対策を取る事があります。
プロンプター
一番手っ取り早いのが、プロンプターという存在です。
オペラとか、昔の洋画などの舞台の場面で時々見かける、舞台前の黒い箱みたいな所から、台本を持ったプロンプターがセリフを言いっています。

お芝居の場合は、写真のようなものでは無く、大抵は舞台装置の裏とか、舞台袖ギリギリに座っています。
私がお願いしたプロンプターは、劇団の若い俳優さんで、稽古の時から稽古場に居てもらい、俳優がセリフを覚えるのもお付き合いしてもらいました。
そうする事で、俳優が忘れているのか、芝居の間なのかという事もわかりますし、俳優がいつも同じ所のセリフが出てこないとか、言い間違えをしやすいとかの癖も把握してもらいました。
そして本番の時には舞台装置の裏にスタンバイしてもらってい、そこからセリフを飛ばしていました。
俳優にとってはとっては難破した時の、灯台の明かりみたいなものです。
カンニングペーパー
それでも、不安な長いセリフとか、ひとり舞台などの場合、舞台装置の壁、小道具の食器の中、机の引き出しなど、あらゆる所へセリフを書いておきます。
刑事役の人なんかは、手帳に書いていました。
ある芝居では、わざわざその為の垣根を作り、垣根の裏に1m×1mのカンニングペーパーを貼っていたこともありました。
もう時効ですから、お話をいたしますと、私が関わった演劇史上最高のカンニンのひとつに
「小沢昭一」さんの舞台があります。
演劇史上最高のカンニング装置
それは「唐来参和(とうらいさんな)」という、もともとは井上ひさしさんの「戯作者銘々伝(げさくしゃめいめいでん)」の中に収録されている小説でした。
これは小沢昭一さんの「ひとり舞台」として、数百回も上演されたものです。
舞台は江戸吉原大門の入り口にある「しんこ細工屋」を営む老婆のひとり語りの舞台です。
※しんこ=白米を臼で引いて粉にしたものを水でこね、蒸し、ついた餅のようなものです。(団子と同じようなもの)
※舞台は、このしんこ細工で「花魁が惚れた男にその証拠として渡す、本物の指の代わりに花魁の指をかた取った、しんこ指を作る老婆の話」
膨大なセリフ量で、1時間喋りっぱなしです。
俳優が複数人出ていれば、セリフを忘れた場合、誰かから助け舟が出る事もあります。
しかし、ひとり芝居では、誰も助けてくれません。
舞台監督と相談した小沢さんは、小道具にある仕掛けをしました。

左は舞台「唐来参和」で「しんこ細工屋」の老婆を演じる小沢昭一。
右は本番中、しんこ細工を作り続ける作業台として使われた、文机の同種のものです。
『唐来参和』小沢昭一さんの生涯最高の舞台のひとつ、
江戸の戯作者の姿が生き生きとわかります。
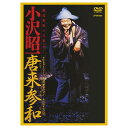 | 唐来参和 とうらいさんな 出演 小沢昭一 DVD VIBF-5477 価格:5830円 |
膨大な台本のセリフを、全て巻物に書き写し、文机の天板部分をそっくり、透明のアクリル板と入れ替えました。
そして、机の中の左側に軸に巻き付けた巻物置き、右側に空の軸を置いて、机の右側の引き出し部分に、巻き取るためのハンドルをつけた、究極のカンニングペーパーを作ったのです。
芝居が始まると、この机の前に座った小沢さんは、アクリル板越しに見える台本を、あたかも覚えているかの如く朗々と語り始めます。
読み終わった部分は、右側に付いている巻取り用の、丸いドアノブ状の取手を右に回わします。
すると、巻物状の台本が左から右へ巻き取られて行く仕掛けです。
机の前面の上部には、万が一、客から覗かれるといけないので、細工作業に使う為の筆立てとか壺とか、茶碗などが置いてあります。
※実際の物をお見せ出来ないのが残念ですが、まあ、門外不出の特殊小道具ですので、上の説明でどうかお許しください。
 | 【中古】 戯作者銘々伝 / 井上ひさし / 光文社 [文庫]【ネコポス発送】 価格:1496円 |
これには、後日談がありまして‥。
舞台「唐来参和」は初日が開いたのち、順調に上演を重ねておりました。
文机カンニングマシーンの効果もあって、小沢さんも毎日快調に演技を続け、観客も湧きに湧いでいました。
が、ある日、小沢さんの様子がいつもと違いました。
芝居中、時々、苦しそうな顔をして、舞台中央から舞台袖にいる我々を探そうと、必死になっています。
一体、何が起きたのか?
体調でも悪いのか?
看護師さん、呼んでおいた方がいいのか?
※この芝居には、観客に急病人が出た事を想定して、楽屋に看護師(当時は看護婦さん)がスタンバイしていました。
しかし、ひとり芝居は芝居中、舞台袖に戻ってくることはできません。
何が起きたのか分からぬまま、終演を迎え、無事、緞帳(どんちょう)が降りました。
本番中、何が起きたのか?
舞台監督が舞台中央のカーテンコールの位置のままで立っている、小沢さんのところに飛んでいきました。
小沢さんは、済まなそうな顔をして「監督‥巻きすぎて、台本‥これ、巻きすぎた時、逆に戻せるようにして」か細い声で言いました。
小沢さん、手元が狂って、巻き過ぎて台本が2ページ飛んだそうです。
早速、舞台スタッフが改良に入り、巻物の左の軸にも取手を付けて、巻き過ぎた時に、戻せるようにした。
後にこの部分はドンドン進歩して、最終的には電動で‥つまりスイッチひとつで、送ったり戻したりできるようになりました。
もちろん、これは小沢昭一さんの、国宝級の演技を阻害する物ではなく、あくまで、俳優と演出家と舞台スタッフたちが考えた、究極の保険でした。
たった1回の面白さ
映画やテレビの記録芸術と異なり、生身の人間が「ライブで演じる舞台芸術」には、1回性の面白さがあります。
観客はいつもは起きないハプニングが、今、目の前で起きた事に、無上の喜びを感じるのです。
私たちは普段気が付いていませんが、宇宙の創生から、今、この瞬間はたった1度しか無く、そこに自分の人生のたった1度と、重なっている人たちがいます。
そんな奇跡を一瞬見ることができるのが、宇宙が出来て初めて起きたハプニングを、俳優や観客たちと共有できたからだと思います。
そう考えると、俳優が時々セリフを間違えたり、言い間違えをする事は、人間にとって、
とても大事な事なのかもしれませんね、小沢さん。
新国立劇場元プロデューサー
中島 豊
大切な物事を忘れた時は、とぼけて寝るか、本当に寝てしまいましょう。








