はじめに
東京は初台にございます、公益財団法人新国立劇場運営財団ですが、名前からして、国立で職員は国家公務員なのか?
なんて誤解されがちですが、私の身分は「団体職員」という名称で、これも最初何のことかよくわかりませんでした、大体なんかの調査にも、会社員、会社役員、学生、主婦、その他ってなってて、いつもその他(団体職員)にしてました。
とにかく公務員でもなんでもなくて(大体、公務員試験とか受けていませんし、みたこともありません)天下り先もありません。
だって、ここが天下り先ですから。
恩給とか無くて、年金は厚生年金で、ちょっとしか貰えません。
新国立劇場の組織も、ヒラから始まって、係長とか課長、部長とありまして、普通の会社の組織とほとんほとんど変わりませんでした。
創設当初の、構成メンバーは日本芸術文化振興会(国立劇場)から3分の1の出向、文化庁(出向)元公務員(天下り)から3分の1そして、そんでもって、そんな人ばっかりじゃあ「オペラ」「舞踊」「演劇」をどうやって作ったらいいのかさっぱり分からないんで、私たちのような民間から3分の1入れました。
最初、日本芸術文化振興会や文化庁から来た、真面目な人達は、民間のそれも癖のある連中の事を、
「野蛮な人達」に見えていたそうです。
大体、文化庁の人とか、組織に逆らわないのですが、民間から来た芸術関係の連中は平気で上司や組織に逆らってました。
「稽古5時で終われ? んなもん、できるわけねえだろ! 役所じゃねえんだぞ、劇場だぞ」
「役者にも、チケット売り場に並べって? それが平等?何言ってんですか! みんな稽古やってんですよ、じゃあ、チケット売り場、稽古が終わる後にも空けといてくださいよ! 午後9時に稽古終わるから!」
我々は結構楽しかったのですが、役所からきた人達は「困った連中だな」と思っていました。
組織的には、部長の上に、常務理事(役員)と理事長がいました。
この理事長は元文部科学省次官とか、元文部科学大臣、或いはあまり天下りが目立ってはいけないと考えたのか、元アサヒビール社長とか、花王の社長とかが就任したこともありますが、ほとぼりが冷めると、またまた、何やら天下りめいた事が起きてくるような感じです。
さ て、その理事長の下にいるのが、常務理事という役員で、定員は3名です。
この常務理事は新国立劇場の中でも、めっちゃ偉い人で、これになるのは、東京大学を卒業し、文部科学省か経団連、はたまた超一流大企業の中でガンガン出世して、めでたく退職した御仁の天下りに限られておりました。
ところが、2014年に新しく就任した常務理事は、大学に落ちて予備校行ったのに、横浜放送映画専門学院という、あのウッチャンナンチャンや出川、バカルディが卒業した学校で、開校当時、無試験で入学できた専門学校です。
卒業後は「芸能座」という劇団の研究生になりました。
あのTBSの「小沢昭一の小沢昭一的こころ」というラジオ番組でお馴染みの小沢昭一氏が座長で、私、結構可愛がられながらも、生意気言ってすぐ辞めて、流れ流れのアルバイト生活をしてました。
その後、なんだかんだで劇団のプロデューサーから新国立劇場のプロデューサー、そして東京大学卒業の人しかなれなかった、常務理事になってしまった‥のです。
それが、この度このブログ
「新国立劇場 元プロデューサー 仕事は度胸、出世は愛嬌」
を書こうといたしまする、わたし、中島豊でございます。
只今は、無職の風来坊、よろしくお見知りおきいただければ、幸いです。

決まって「中島!なにニヤニヤしてんだ!テメエ舐めてんのか!」
とか、言われてました。
わけて皆々様方に御願い申しああげ奉りまするは、未熟不勉強、才能少なしの中島で御座りますれば
、御目まだるい所は、袖や袂で、幾重にもお隠しあって、よき所はあちらこちらへの褒め称えの御喝采、七重の膝を八重に折り、すみから、すみまで、ズズズイットウーー、オン願い申しああげ奉ります。
2024年12月4日 中島豊
生まれてから、演劇専門学校入学まで
1955年(昭和30年) 0歳
4月 神奈川県逗子市に、小さな写真店の長男として誕生
1971年(昭和46年)16歳
4月 地元の公立中学を卒業し、県立逗子高校に入学
中学の卒業生200人の35番〜70番までの生徒が進学する地元の学校です。
私は70番だったので‥ギリギリのギリの下くらいでした。

現在は県立逗子葉山高校となっている
1974年(昭和49年) 19歳
2月 大学受験。
第一志望!青山学院大学文学部、受験会場は思った通り、9割以上が女子。
しかもかなり美人でいい香り。
青学女子と原宿を歩く自分を想像し燃える!
1時間目、英語、第1問の長い長い問題文を、読み終わら無いうち終了のチャイム🎵
燃え尽きた
4月 高田馬場にある早稲田予備校に入学。
予備校だけでも、早稲田という名前にしてみた。
来年は、最低でも青学、できれば早慶上智の合格を決意。
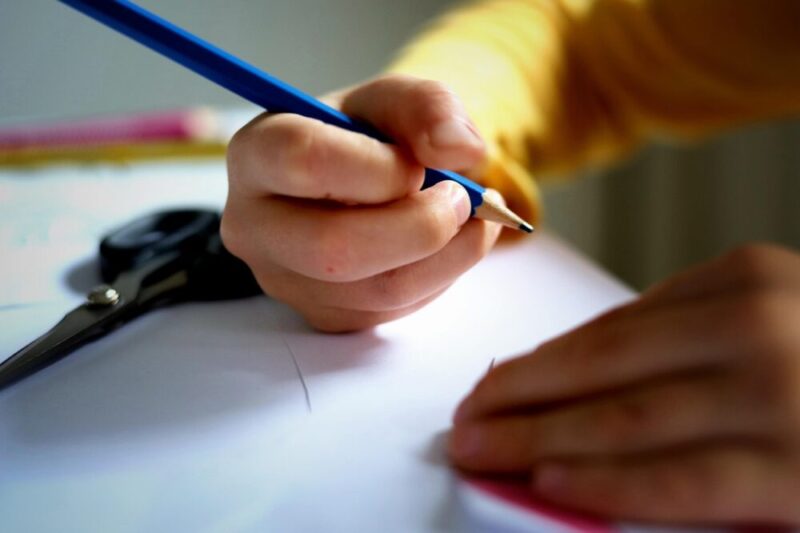
5月 予備校で東京出身の連中と知り合う。
新宿界隈の面白さを教わる。
3本立て映画をハシゴし、ゴールデン街で全共闘世代の自称作家や役 者、映画関係者らと知り合い、酒とタバコと麻雀、ついでにマルクスを覚える。
フランスのルネ・クレマン監督に憧れ、将来は映画監督を志すことに。
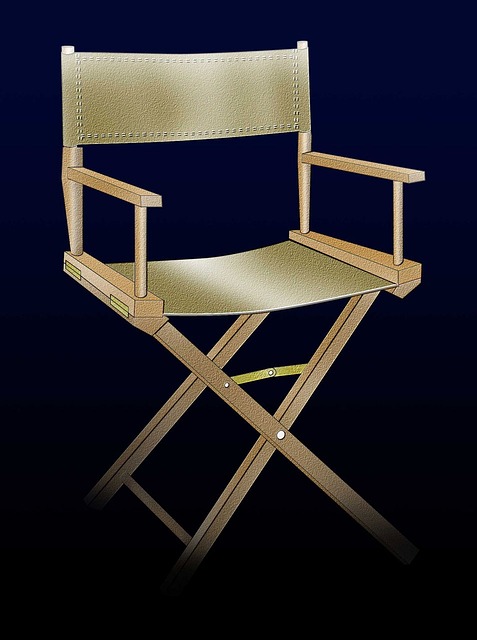
8月 予備校の進路相談
進路指導担当教師に、映画監督志望を話す。
教師「映画監督になるのは、東大か最低でも早稲田あたりだね、来年は‥無理かもね」
「 ‥‥」
相談室を出ようとする背中に。
「キミは成績悪いんだから、変なこと考えないで、ちゃんとした道に進んだ方がいいよ」
励ましのお言葉
10月 模試の結果は現役時代と変わらない、遊んでばっかりだったからと、成績を正当化してみるも、どう考えてもこのままでは、青学はおろか日東駒専も危ない、再び予備校の進路指導の教師のもとへ
教師「大学なんて、超一流じゃなければ、どこだっておんなじだよ、Fランでもどこでも良いから、入れてくれる大学へ行きなさい」
再び励ましのお言葉
11月 映画監督志望に挫折して落ち込んでいたら、映画監督の今村昌平が、翌春4月に横浜に映画学校を開校するという新聞ニュースが目に入った
演劇専門学校時代
1975年(昭和50年)20歳
4月 2年制の横浜放送映画専門学院演劇科(現・日本映画大学)へ入学。
新設校の1期生、先輩がいない、しかも無試験ということなので、これ大学より面白いかも!
浪人させて予備校まで行かせたのに、結局、大学も受けず、横浜放送映画専門学院とかいう、
胡散臭い学校の演劇科へに行ったので、両親は泣いた‥号泣した。
父「どこでもいいから、大学受けろ!」
中島「受かったって、行かないからもったいないじゃん」
父「そんなこと言って、落ちるからだろ」
中島「もう、映画の学校へ行く事にしたから」
父)この子、‥‥おわった‥本当に‥終わった
母)写真屋継がせましょう。
当時、横浜放送映画専門学院には、映画、テレビ、脚本文芸、演劇の4つの科があったが、今村昌平が直接 面談するという、入学前のガイダンスに行くと、映画科や脚本文芸科は、入学希望者に国公立や早稲田や慶應など、一流大現役生や卒業の社会人などが多く、太刀打ちできそうになかった。
やべぇ
と、思っていたところ、日本でも、海外でも俳優が映画監督をやっているケースがあると知ったので、そうだ、演劇科に入って、スターになれば、映画監督できるかもしれないし、
演劇科なら女優志願の可愛い女の子もいっぱいだろうから、一石二鳥!
演劇科に入った‥。
入ってみたら、演劇科はどちらかというと、ほっぺの赤い田舎の娘ばっかりだった。
知的で美しい大人の女性は映画科や脚本文芸科の方にいた。
※この辺りの今村昌平初め、映画・演劇関係者が作った新設校入学の話は本編ブログにて執筆予定
演劇科に入学してみると、1年生の間は、朝から晩まで、肉体訓練と称した、マット運動や腹筋、柔軟、タップダンスや歌唱、ジャグリングなどがあり、運動部のようなカリキュラムに辛くて、タレント志望の学生は半数が辞めていった。
中島は、辛い授業には出ないで、楽な授業だけ出て、後はアルバイトしたり、酒飲んだり、麻雀したりの毎日だったので、挫折組には入らなかった。
1976年(昭和51年)21歳
1年時の著しい出席日数不足で、2年生への進級が危ぶまれたが、学生の半数が退学していたので、学校は見て見ぬふりをして進級させてくれた。
2年生になると、朝から晩を過ぎ、夜9時位まで芝居の稽古、稽古、稽古だった。
さすがに、これは自分の出演する役が付いていたので、サボるわけにいかず、比較的真面目に稽古に出ていた。
この頃、つかこうへい、井上ひさし、鈴木忠志、唐十郎、小沢昭一、木村光一、
串田和美などの舞台に多く触れ、映画監督志望は、演劇の演出家か劇作家に変わった。
卒業、劇団芸能座研究生から、こまつ座プロデューサーになった
1977年(昭和52年)22歳
3月 2年制の横浜放送映画専門学院を卒業し、倍率15倍を突破して、俳優の小沢昭一が主催する、
劇団芸能座演出部(スタッフコース)研究生となる。演出家か劇作家になるには、役者なんかやってないで、スタッフ・コースにいた方がいいと考えた。
演出部の試験会場には、現役の舞台スタッフや東大卒とかの、凄そうな人がたくさんいたのに、どうして自分が合格したのか、試験官をしていたY舞台監督に尋ねたら「お前、落ち込みそうになかったから」だった。
芸能座は当時大人気の、中年御三家(野坂昭如・小沢昭一・永六輔)の一人、小沢昭一が設立した劇団で、普通の劇団がチケット3,000枚売るのに四苦八苦している時に、10,000枚が即日完売するスーパー劇団だった。
劇団員には小沢昭一のほか、加藤武、山口崇、山谷初男などがいた。
後に新国立劇場の演劇芸術監督になる栗山民也が、2年先輩の演出部研究生だった。
芸能座は小沢昭一と早稲田で同級生だった、今村昌平学校の第1期卒業生ということで、特別に1次試験(書類審査)免除の特典があった。
横浜放送映画専門学院からは5人受験したが、中島だけが合格した。
私以外は、俳優志望だった。
小沢昭一さんも、流石に親友の作った学校の1期生を、全員落とすわけにはいかないから、
とりあえず無難なスタッフ・コースで一人合格させておこうと考えてくれたのかもしれない。
劇団に入団してからは、劇団の東京公演の後、北海道旭川から九州鹿児島まで、
全国公演の舞台スタッフとして周り、各地の名産を食べ、名所旧跡を観光し、毎日小沢昭一さん他、
名優の舞台を見て、時々、楽屋に届いた珍しい差し入れを食べて、
毎日毎日、遊ぶように仕事をして暮らしていた。
1978年(昭和53年) 23歳
折角合格した劇団芸能座なのに、3作品目の公演スタッフをしてた頃、
やっぱり演出家より井上ひさしやつかこうへいのような劇作家になりたい!
そう思って、劇団をやめてしまった。
※後年、このお二人(井上ひさし・つかこうへい)とは縁あって、
一緒に仕事をさせてもらった。
劇団を辞める時、小沢昭一さんの楽屋に呼ばれた。
叱られるかと思って、神妙な顔で楽屋に入ると、目に涙を溜めた小沢昭一さんが
「今まで、本当にありがとう‥何も、何もしてあげられなくて‥ごめん」
そう言って、両手で私の両手を握ってきた。
この人は、どこまで行っても俳優だと思った‥
私もできるだけ頑張って、必死で泣きそうなのを我慢する顔を見せながら、頭を深くさげ、涙が出てない目を見られないようにしながら、
「‥すみません!」
そう、声を震わせて返事をした。
横浜放送映画専門学院での、俳優修行が役に立った。
1979年(昭和54年) 24歳
葉山にあった冷凍食品会社の倉庫で、防寒着を着ながら商品の出し入れをする、アルバイトをしながら、六本木の放送作家組合が開催していた「放送作家教室」なるものに通い出し、劇作家を目指した。
師事した先生は「寺島アキ子」という劇作家・放送作家だった。
厳しい先生で、ちょっとでも、台詞や劇構造が変なものを書くと、コテンパンにやられ、なにげに言い訳でもしようものなら
「馬鹿モン!」
「人を見ろ、人を!、人を描くんだ!」
「嘘書くんじゃない!」
「頭だけで書くから、魂がないんだ!」
「だいたい、お前は!」
罵倒に次ぐ罵倒だったが、いちいちごもっともな指摘なので、むしろ心地よかった。
同じ志の数人が師事していたが、罵倒されなくなった者から辞めていった。
これ、今だったら「パワハラ」とか言われるのかな?
1980年(昭和55年) 25歳
横浜放送映画専門学院時代の仲間と、小さな劇団を作り堀場栄というペンネームで芝居を上演した。
「アメリカン・イエロー」という作品をアートシアター新宿という小さな劇場で上演した。
劇団を作ったが、それで食えるようにはならず、どこにでもいる演劇青年のように、それから3年ほど、冷凍倉庫でアルバイトをしながら戯曲を書いたりしていた。
1981年 (昭和56年) 26歳
戯曲の方はなかなか良いものが書けず、劇団も年一回の公演がやっとだった
アルバイトの方は、根っからのお調子もんが幸いして、バイト先「シュガレディー」の監督や幹部社員から可愛がられ、年度末には成績優秀者として金一封を貰い、正社員への誘いを受けていた。
愛嬌のふりまきは、得意だった。

1982年(昭和57年)27歳
一旦業界から離れていた恩師のY舞台監督が、業界復帰するから手伝えと言われ、劇作家修行も行き詰まりを感じ、アルバイト生活にも少し飽きてきたこともあり、小沢昭一主催の「劇団しゃぼん玉座」旗揚げ公演に参加する
※劇団芸能座は5年で解散するという、時限劇団だった。
私が退団した2年後に芸能座は解散した。
その後、小沢昭一は「劇団しゃぼん玉座」という小沢昭一ひとり劇団を旗揚げした。
1983年(昭和58年)
しゃぼん玉座旗揚げ公演の最中から、公演終了後の、舞台スタッフの仕事の依頼が次々に来た。
以後、どこの演劇集団にも所属しない、フリーと呼ばれる舞台スタッフの身分になって、様々な劇団の舞台スタッフの仕事をするようになった。
主な参加劇団は、五月舎、地人会、しゃぼん玉座、劇団飛行船など
舞台スタッフの仕事が忙しく、戯曲を書く時間が無くなったが、収入はバイト生活より多かった。
こまつ座プロデューサーから、英国留学まで
1984年(昭和59年)29歳
「お前、劇団こまつ座のプロデューサーやれ!」
「プロデューサー? 私が?」
「舞台スタッフより向いてるかもしれない、お前、落ち込みそうにないから」
芸能座の試験官だった、恩師のY舞台監督から突然そう告げられた。
こまつ座はその年の春に「頭痛肩こり樋口一葉」で旗揚げをした劇団で、座付作者が井上ひさし、座長が当時、井上ひさしの奥さんの井上好子さんだった。
プロデューサーって、何するのか知らなかったけど、名前がカッコいいのと、天才作家井上ひさしの側にいれば、絶対戯曲の勉強になると思った。
「わかりました、やらせていただきます!」
こまつ座に入ると、座長の井上好子さんとベテラン・プロデューサーの安さんがいて、後は、経理とチケットの女性職員が3名だった。
こまつ座は俳優が所属しておらず、公演ごとに様々な劇団やプロダクションに連絡して、公演に適した俳優に出演交渉し出てもらう、当時、珍しい「プロデュース・システム」の劇団だった。
当初は公演担当プロデューサーという仕事で、チーフの下で、旅公演の移動行程作成や切符の手配、ホテルの部屋割り、食事代やタクシー代金などの支給作業などをしていた。
最初に担当した公演が「蒲田行進曲」でブレイクした直後の平田満と「遠来」の石田えりが主演の「日本人のへそ」その次が、女優ばかり6人の、劇団こまつ座の代表作「頭痛肩こり樋口一葉」で、有名な俳優や日本有数の腕利きスタッフたちとの、日本全国を周る旅公演の日々は、楽しくて、楽しくて仕方なかった。
1986年(昭和61年)31歳
ところが、1年半後、大事件が起きた。
井上ひさし・井上好子夫妻が離婚した。
夫婦の関係修復に奔走していた、プロデューサーの安さんは、その少し前に劇団を辞めてしまっていたので、先輩も劇団の代表もいなくなってしまい、翌年、井上ひさしの長女の井上都が社長として就任するまでの間、実質的な劇団運営を任された。
※離婚に至る深夜の出来事や、離婚発表記者会見の東宝のプロデューサーの記者会見での仕切り、上演中の公演の事、この辺りの詳細はブログ本体で書くことにする。
若干、31歳で当時観客動員数20万人の劇団の舵取りをすることになった。
エライ事になった‥それまで、旅公演ばかりしていたので、東京での予算管理や執行、キャスティングや地方公演の売り込みなど、全くわからなっことだらけだったが、周りが不安がるといけないので「予算作り? 簡単、簡単、配役作業? お茶の子サイサイ、ハイサイサイ! 地方公演営業? 寝てたって出来るよ!」
ただただ、ハッタリとクソ度胸で切り抜け、裏ではコソコソ、あちこちの劇団のプロデューサーに教えてもらいに行っていた。
1987年(昭和62年)32歳
登記上の代表だった井上ひさしに変わり、長女の井上都が社長に就任。
劇団の大番頭(チーフ・プロデューサー)として、上演演目の決定やキャスティング、スタッフィング、全国ツアーの営業展開などのプロデューサーとしての仕事をするようになる。
その頃には、ハッタリもどうにかこうにか、やらずに済むようになっていた。
以後、こまつ座は全国公演を含め年間平均350ステージの舞台を上演する、国内の劇団の中でも有数の上演回数の多さを誇る劇団となった。
各劇団のプロデューサーたちは、皆、50代、60代の大ベテランだったので、子供の頃から、あまり頑張らない方だったが、この時だけは馬鹿にされないように、必死で頑張りつつ、得意の愛嬌で取り入ってた。
※この辺りの、他の劇団が気が付かなかった、裏技的なプロデュース方法に関して、本編ブログにて記述予定。
1995年(平成7年) 40歳
新作公演の初日延期や、俳優の交代劇など、様々な出来事を経ながら、こまつ座で10年ほど過ごした頃、文化庁の新進芸術家海外研修制度に応募して合格。
英国留学から新国立劇場に入って、偉くなったとこまで
英国・ロンドンに留学。
研修先は「ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー」「アーツ・カウンシル・オブ・イングランド」
文化庁の留学試験は書類提出と面接のみ。
劇団のチーフ・プロデューサーをしていたおかげで、面接官は演劇界の知り合いばかりだった。

英語学校のクラスメイトはフランス、イタリア、ポーランド、中国、ユーゴ、チリなどの人たちだった。
※応募方法や合格の秘訣などは、後年、審査員をした経験などを含め、本編ブログにて掲載予定
帰国後、翌々年に初台にできる第二国立劇場(現・新国立劇場)、演劇部門のプロデューサーとのお誘いがあった。
※ロンドン留学顛末記はブログにて記述予定
1996年(平成8年)41歳
財団法人新国立劇場制作部演劇に入職
私の入職時点での制作部員は私を含めて5人、内ひとりはデスクの女性だった。
新国立劇場は特定の俳優が所属しておらず、プロデュース・システムで公演を行う劇場だったが、私以外の4人には、プロデュース・システムの経験がなかった。
1997年(平成9年)10月新国立劇場開場 オペラ・バレエ・現代舞踊・演劇の4部門を擁する、
日本で最初の現代舞台芸術の国立の劇場がオープンした。
2000年(平成12年) 45歳
12月 演劇・総括プロデューサー(制作の総責任者)に就任
11年間のこまつ座の経験が生きて、予算作成や執行に他の人たちより、少しだけ出来たからかな
2001年(平成13年) 46歳
9月 3年前から企画、交渉を続けていた、日本初「パリ・太陽劇団」(テアトル・ドゥ・ソレイユ)の来日公演を敢行。
フランス人スタッフと色々喧嘩しながらも、最後はお互い歓喜の中での千穐楽を迎えることができた。
2002年(平成14年)47歳
4月 演劇・チーフ・プロデューサーに就任
※総括プロデューサーとチーフ・プロデューサーとは何が違うか?
やる事に何か変わることは無かったので、よくわからないが、
なんか副参事とか云う位になって、給料があがった。
※プロデューサーとして制作に携わった作品数は、こまつ座時代から新国立劇場制作部から、
営業部に移動になるまで、200作品以上になった。いくつかの作品のエピソードやプロデュース法
などはブログにて掲載予定

みたいな感じがするでしょ。
とりあえず、仕事はカタチから入って、相手をビビらす。
ハッタリ作戦でした。
2005年(平成17年) 50歳
4月 桐朋学園芸術短期大学の非常勤講師として、週1回2時間の講義を受け持つ事になる。
これは、2014年のステージ・クリエイト科の閉科まで続けた。
担当授業の始業が9:00だったので、自宅を7:00過ぎに出なければならず、
予備校以来の超満員電車に乗った。
自分で言うのも何だけど、結構、人気の先生だった。
ここの卒業生の何人かは、現在、色々な現場で仕事をしている。

2011年(平成23年)56歳
4月 営業部長に就任
部長就任直前の3月、オペラ研修所の卒業公演時に「東日本大震災」が起きる。
当日は400名以上の人が、一般開放した新国立劇場のオペラ劇場内で、一夜を過ごした。
当初、400名ほどの避難者だったが、ネット上に「新国立劇場が解放されている」という言葉が出て、
時間を追うごとにオペラ劇場の避難者が増えていった。
最終的には700名ほどとなった。
営業部員が徹夜で、クッションシートを出したり、非常用の食料を無償提供したり、大型モニターを仮設し震災の状況をライブで提供したりした。
みんながいる所から離れた、ロビーの隅に若いカップルがいた。
我々の静止を聞かず「渋谷まで歩いて行ってみる!」と言って聞かない。
ウチはとこか? と聞くと千葉だと言う。
千葉ならここにいたほうがいいのでは?
と言っても、どうしても渋谷まで歩くと言う。
よく見ると、女の子は下を向いて恥ずかしそうにしていて、男は目が爛々と血走っている!
魂胆が見え見えだが、無粋なことは言わず「じゃあ、どうぞ」と言って見送ったが、3時間後、戻ってきた‥どこのホテルも🈵だったとのこと。
2011年〜2013年
人事異動で、部下になった営業部員が優秀で、私が担当していた演劇部門の公演は常に目標を達成、開場以来の好成績が続いた。
私は特にやることもなく、部下の部員たちと色々なイベントを考えて、楽しく仕事(遊んで?)していた。
そのイベントが素晴らしいと、直属の常務理事が大変気に入ってくれ、一緒に食事をしたり、野球を見に行ったりしていた。
2014年(平成26年) 59歳
5月 営業会議中に突然、理事長に呼び出された。
理事長室に歩きながら、何か落ち度がなかったか必死に考えた。
何も思い浮かばないが、何かあったから呼び出されたのだろう。
俯きながら、理事長室に入った。
理事長「ああ、君ねぇ、次の評議委員会と理事会で、君の常務理事就任を、皆んなに図るから、まだ誰にも云うなよ、まあ、奥さんにぐらいなら言ってもいいや」
中島 「えっ! あのぉ、そんなのあるんですか?」
新国立劇場の常務理事は3人で、内訳は文科省、経団連、あるいは日本有数の大企業からと決まっていた。
理事長「そろそろ、職員から常務理事が出ないと、劇場で来てから20年だしなあ‥いいな、まあ、
理事会であいつはダメだとか云うのが出たら、ダメだけど、そんな人いないだろ? 」
細かい経緯はわからなかったが、会議を通過すれば、新国立劇場初の職員からの
常務理事の誕生になりそうだった。
6月 理事会・評議委員会
この辺りはさすが文科省の天下り役人の理事や総務部長で、事前に評議員と理事の何人かに、私の常務理事就任の下打ち合わせを終わらせていた。
会議での人事案件は、5分で終わり、常務理事就任が決まった。
役員には秘書が付いた。
朝、新聞とお茶を持ってきて、今日の予定を告げて行く。
そのほか、職員からの相談や決済事項の説明などで、役員に会いたいときは直接ではなく、秘書を通して伝えてくる。
自分自身は何も変わっていないが、周りがどんどん変わって行ってしまいました。
財界や政治家、各国大使との会談や会食が増えた。
危ないのは、自分が変に偉くなったと錯覚してしまうこと。
これは、周りの扱いが下手に下手に出てこられると、つい錯覚してしまって、そうじゃ無い扱いを受
けると「ムカッ💢」と来てしまうことが私もあった。
これは側から見ると、とっても、とっても、とってもカッコ悪いのです。
これやると、モテないし、出世はしません!
2020年(令和2年)6月
無事、6年の任期を終え、定年退職となる。
なんで、常務理事になったのかなど、具体的な説明は後半、随分と端折ってしまったが、これから書くブログに色々書いていきたいと思っていますので、長いプロフィールはこの辺にて、幕を下ろします。
みなさま、ご精読ありがとうございました。
今後のブログをお楽しみいただければ幸いです。
精一杯、書いてまいりますので、よろしくお願いいたします。
元演劇プロデューサー
中島 豊